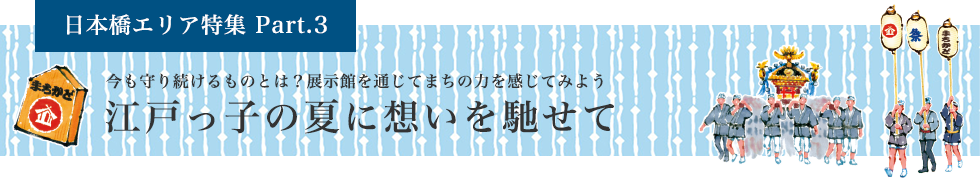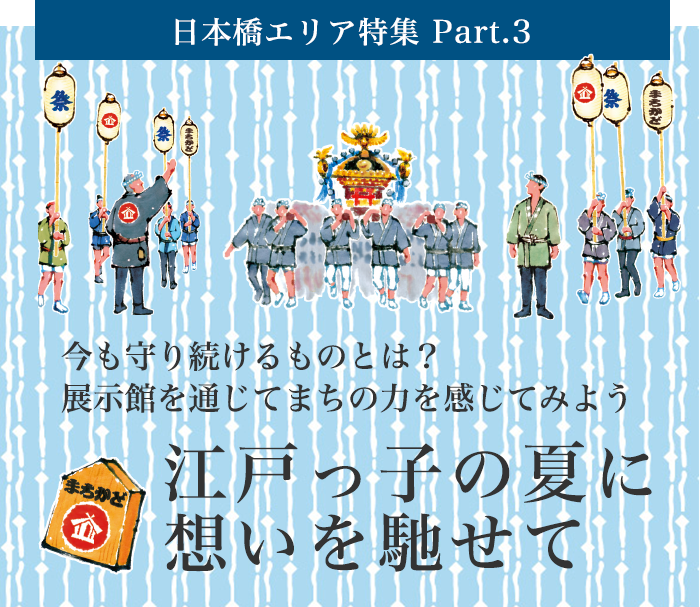- ―お祭の衣裳は作っていますか?
- 前の東京オリンピック頃まで、夏祭にはよく柄から作った揃いのゆかたを着ました。今は神輿の担ぎ手は皆袢纏(はんてん)ですが、昔はゆかたを着る所も多かったです。長年うちで作っている町会さんもいますよ。
- ―ゆかたはいつ頃広まった?
- 江戸では大名達が登城する際に裃(かみしも)の下に小紋を着たため、型紙を使って反物を染める小紋職人が三百人いたと言います。また湯屋が江戸に何百軒もでき、入浴後2階で飲んだりする庶民の社交場になりました。そこでゆかたが着られ始め、天保期に贅沢を禁じられた庶民は裃小紋の小さな柄を綿の着物に取り入れたようです。長い板の上で小紋よりやや大きい中形の柄を付けるため、当時はゆかた地のことを「長板中形(ながいたちゅうがた)」と呼びました。幕末には小紋職人の半分がゆかた職人になったとされ、明治以降大流行したんです。
- ―お父様は人間国宝でしたね
- 父の幸太郎は、三勝の専属職人だった祖父に中学の頃から弟子に入りました。私が子供の頃、父は一年中ほとんど家の隣の板場(いたば)(作業場)にいました。「長板中形は10歳から修業しないと一人前の職人にはなれない」とよく言っていましたね。今ではこの辺でゆかた製作は3軒となり、長板中形ができる職人は数人ですが、できる限り残していきたいですね。

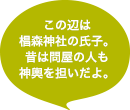
お話を伺った方館長
清水 敬三郎さん

三勝ゆかた博物館
管理者:三勝株式会社(平成23年度認定)
東京都中央区日本橋人形町3-4-7
03-3661-8859(10:00~17:00)
開館日:月~金(祝日・年末年始等を除く)※要予約
開館時間:①15:00~ ②16:00~(2部制)
最寄り駅:人形町駅A5番出口 徒歩2分
HP: http://www.sankatsu-zome.com/
※臨時休館や開館時間短縮の場合があります。
詳しくはお問い合わせください。